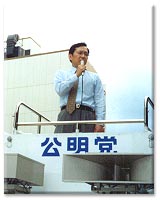�����}�p���`(���̂W)
![]()
![]() �@Q.
�����}�́u�N���P�O�O�N���S�v�����v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���
�@Q.
�����}�́u�N���P�O�O�N���S�v�����v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���
![]()
�@�l�X�Ȑ��_���������Ă��A���{���ŗD��Ŏ��g�ނׂ��ۑ�Ƃ��āA�u�i�C��v�ƕ���Łu�N�����ÂȂǎЉ�ۏᐭ��v���������Ă��܂��B���Ɂu�N�����x�v�͍���҂����łȂ��A�q�ǂ����瓭������̂��ׂĂ̍����ɂƂ��ďd�v�ȉۑ�ł��B�Ⴂ�l�X�̒��ɂ͔N���ȂǏ������炦��Ȃ��Ƃ��đS������Ȃ����������悤�ł����A����͂Ƃ�ł��Ȃ����ł��B��b�N���͊m���ɋ��t�z�Ƃ��Ă͖����̂������̂ł͂���܂��A������|���Ă����Ȃ��������߂ɓ����Ȃ��Ȃ��Ă���ꂵ��ł���l�������̂ł��B�܂������鎞�ɏ\���Ȓ��~�����Ă��̌��{�Ɨ��������ŘV���H�ׂĂ�����悤�Ȑl�͋ɂ߂ċH�ł��傤�B�o�ς��ᐬ���̎��ケ���A����Љ�����S���Đ����Ă䂯��悤�ɁA�݂�Ȃŏ��������N�����x���ێ�����K�v������܂��B
�@�����}�ƍ�������J����b�͂��̂悤�Ȋϓ_�ɂ����āA�P�O�O�N��܂ł�W�]�����u�N���P�O�O�N���S�v�����v���Ēv���܂����B�}�X�R�~�͂���܂ŋ������Ȃ̔N�����v�Ăɑ��Ĕ��{���v�摗��ł���Ɣᔻ�I�ł������A����̍�����Ăɂ��Ă͂Ȃ��Ȃ��]�������Ă���悤�ł��B����͍����b������܂Ŗ�������Ύ�����Ȃ������u�N���ϗ����v(�P�S�V���~)���������A�����̐��オ���N���z�̒�グ�Ɏg�����Ƃ�F�߂���������ł��B�������ő�̗��R�́A�u�c��̐���Ƃ��̎q�ǂ������̔N�����I���Q�O�U�O�N����܂ł̔N���������ł��ꂵ���̂ŁA���̎��ɐϗ��������t��Ɏg�������v����ł��B���v�����ł͂��̐ϗ������Q�P�O�O�N���_�łP�N����Q�T���~���c��悤�ɂ��܂��B
�@����͑�ςȔ��{���v�ł��B�����b�Ɩ����Ƃ̌������Η�������܂����B�������A����ɂ���ĔN���̋��t�������u���𐢑�̕��ώ����̂T�O���ȏ�A�ł���T�T�����x�v���m�ۂł���킯�ł��B���݂̐����͂T�X���ł��B�ϗ������ێ�����]���̕������ƁA���q����������x(�P�D�R�X)�Ȃ猻�ώ����̂T�Q�D�W���A���q�����i�s�����ꍇ(�P�D�P�O)�͂S�V�D�W���Ƌ��t���T�������荞��ł��܂��܂��B����A�ϗ������g�����v�����ł́A���q�����i�s���Ă��T�P�D�Q���A���q����������x�ł���T�S�D�T�����m�ۂł��܂��B�Ȃ����v�����ł͐��{�͂T�N���ƂɌ������X�T�N�Ԃ̔N���������������Čv�����蒼���A�Q�P�O�O�N�ȍ~���ϗ�����������Ȃ��悤�ɂ��܂��B
�@����ɓ��v�����ł́A�����N���͕ی������������u�N���̂Q�O���ȓ�(�J�g�ܔ�)�v�ɗ}���邱�ƁA�����N���͍��ɕ��S�������R���̂P����Q���̂P�Ɉ����グ�A�������[�߂��ی����̂P�D�V�{�ȏ�̔N��������u���P���W��~��܂łɂƂǂ߂�v���Ƃɂ��܂��B���̂悤�ȁu�ی����Œ�����v�ɂ���ĕ��S���ߓx�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��܂��B
�@�����̉��v�ɂ���āA���q������i��ł��N��������������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��ł��A��������قǔN�����t������Ƃ̍����̕s��(����Ԋi��)��a�炰�邱�Ƃ��ł���̂ł��B
��
�����}�p���`(���̂V)
![]()
![]() �@Q.
�����}�̃}�j�t�F�X�g�͂ǂ̂悤�ȓ���������̂ł���
�@Q.
�����}�̃}�j�t�F�X�g�͂ǂ̂悤�ȓ���������̂ł���
![]()
�@���}�̒��ōŏ��Ƀ}�j�t�F�X�g���o�����̂������}�ł��B�����}�▯��}�͐������}���߂����ƌ����Ȃ���A�����ɂ��̌��Ă������ɒł��Ă��Ȃ��ł��B�O�c�@�I�����ԋ߂ɗ\�z����钆�ŁA���̑̂��炭�ł͕��i����^�ʖڂɐ��������Ă����Ƃ͎v���܂���B�܂�����܂ŏ���ň��������ȂǑI���ړ��Ă̖��ӔC�Ȍ���Ɣᔻ�����ɏI�n���Ă������Y�}�Ȃǂ͘_�O�ł��B
�@
�@�����}�̃}�j�t�F�X�g�͑傫��3�͂��琬��A���̓����͐����҂⏎���E��O�̎��_�Ŋт���Ă���A��̓I�Ȑ���̐��l�ڕW������̗��Â��A�B�����������ȂǁA�ɂ߂Č��I�ő����̖��}�h�w�̕��X�ɂ��������Ăԓ��e�ƂȂ��Ă��邱�Ƃł��B
�@
�@��P�͂́u���_����|�B�O�ꂵ���s�v�A�����̔r���v�ł��B���Ƃ��A�u�������ƃR�X�g��20%=1��8�牭�~���팸�v��u�����������P���팸�B��36���l�A���^�x�[�X�Ŗ�2���~�̍팸�B�v�u���ƌ�������1�����P�ʂŎx������Ă���ʋΎ蓖���U��������ɐ�ւ��邱�Ƃɂ��A��75���~���팸�B�v�Ȃǂ́A�����Ō�������Ȍ����}�łȂ��Ă͂ł��Ȃ�����ł��B
�@
�@��Q�͂́u���S�E�͂�Љ�̍\�z�v�ł́A�킪���̌o�ώЉ�𐢊E�I�ȋ����ɓK���ł��銈�͂ɖ��������̂ɓ]������ƂƂ��ɁA�����ɉ��v�ɔ����u�ɂ݁v���ɘa���邽�߂̃Z�[�t�e�B�l�b�g(���S��)�̍\�z����Ă��܂��B
�@
�@�u�����C�̂���N�ƉƂ��x�����A100���Ђ̋N�Ƃ��߂����v�ق��A�u��_�ȋK�����v�Ɗ��A�o�C�I�A�i�m�e�N�m���W�[�Ȃ�21���I�^�Y�Ƃւ̏d�_�����A�܂��ό��U���Ȃǂɂ��V���Ȍٗp��500���l�n�o�v���܂��B���킷��l���������A�����l�X�ɖ���^������̂ł��B���Ɂu���Z�@�ւ�������Ǝ҂ɑ��l�ۏ����߂Ȃ��Z���̌������N�v���Ă���_�͏d�v�ł��B
�@
�@�����Ō��ݐ[���ȏɊׂ��Ă���u��N�҂̎��Ɨ����v�����邱�Ƃ�傫�ȖڕW�ɂ��Ă��܂��B��N�҂ɑ���A�Ǝx���T�[�r�X����̓I�ɍs���u�W���u�J�t�F�v
�̐ݒu��A�u���{�Ńf���A���V�X�e���v(�Ⴆ�ΏT�̑O���͊�ƂŎ��K���A�㔼�͐��w�Z�ȂǂŌP�����Ȃ��琳���̗p�ɕK�v�ȗ͂�����)�̓����ł��B�w���̊F����ɂ́A�u���w���Ώۂ̏��w�����x�v�̑n�݂Ȃǂ��A�s�[�����Ă��܂��B
�@
�@������q�ǂ������̂��߂ɂ́A�u2004�N�x���Ɏ����蓖�����w�Z�R�N���܂łɊg�[�v���邱�ƁA�u�H�i�̃g���[�T�r���e�B�[�V�X�e���̓����v�A�u�S���w�Z�ɃX�N�[���J�E���Z���[��z�u�v���邱�ƁA�������L�̐g�̓I�E���_�I�s���ɂ��đ����I�ɐf�Âł���u�������O���v�����邱�Ƃ��Ă��Ă��܂��B���s�s���a�@�ł́A�����}���s�s��c���c�̓w�͂�����10��1������J�݂���邱�Ƃ����܂�܂����B�����͌����}�炵�������҂̎��_�ɗ������f���炵������ł��B
�@���č���Ґ���ł͉��Ƃ����Ă��u�N�����x�̔��{���v�v���d�v�ł��B�����}�́u��b�N���̍��ɕ��S�����͂R���̂P����i�K�I�Ɉ����グ�A2008�N�x�ɂ͂Q���̂P�Ƃ��܂��v�B�u�����グ�ɔ��������́A�����ł̒藦���ł̌������ƔN���ېłɂ��m�ہv�v���܂��B����͓�������̕ی������S��}����ƂƂ��ɁA�����N���������x���邱�Ƃɂ��A�����ɔN�����x�ւ̈��S���������Ă��炤�_��������܂��B�܂����̂悤�ɋ�̓I�ȍ����ɂ��Ă������Ă���Ƃ��낪�]���̌���Ƃ͈قȂ�A����Ɉ��Ղɏ���ł������Ƃ��Ȃ��_�ɂ��Ă��悭�l�����Ă���_�ł��B
�@100�N��܂ł�W�]�����u��������J����b�̔N�����x���v���āv�ƂƂ��Ɍ��Ă���������A�����}���ǂ̐��}��������Љ�̈��S�̂��߂ɐ^���Ɏ��g�݁A�������D�ꂽ�������Ă��邱�Ƃ������ł��B
�@��
�����}�p���`(���̂U)
![]()
![]() �@Q.
�C���N�x���@�ĂɂȂ��^�������̂�
�@Q.
�C���N�x���@�ĂɂȂ��^�������̂�
![]()
�@�����ɂ��̎����������������̂ŁA���Ȃ�̍l�����q�ׂĂ����܂��B����̃|�C���g�́A�u���q�����C�O�܂ŏo�����Ă����ƁA�푈�Ɋ������܂��\���������B�v
�u�����}�͕��a�̓}�Ȃ̂ɁA�푈���͂ɉ��S���邱�ƂɂȂ�v�Ƃ����_�ł��B�܂����Y�}�̂���c���Ȃǂ́u�l�E����e�F����@�Ă��v�ȂǂƁA�X�������łƂ�ł��Ȃ�����`���J��Ԃ��Ă��܂����B
�@���͂܂��C���N�̑����̍������A����H�ƁA��ÁA�ߗ��Ȃǐ����Ă�����ōł���{�I�ȂƂ���ŋꂵ��ł��鎞�ɁA�Ȃ��x�����Ȃ��̂��Ɩ₢�����̂ł��B���q���͐푈�����邽�߂ɃC���N�֍s���̂ł͂Ȃ��A�l�������̂��߂ɍs���̂ł��B����ɑ��āA���̂悤�Ȋ����͖��Ԑl�ł��ł���Ƃ������_������܂����A�C���N�̔�Џ̓{�����e�B�A�Ȃǂłق��ڂ��Ƃ���悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B���Ƃ��Ă̑g�D�I�ȏE������������i�̋������s���ł��B���`���[����PKO�����ł����q���͓��l�̎��т�����܂��B
�@�܂����A�ł́A�T���Q�Q���ɃC���N�푈��̕ĉp�R�哱�̓�����F�m����ƂƂ��ɁA�C���N�ւ̖{�i�I�Ȑl���E�����x�����������ɌĂт����錈�c1483�����̑����Ă��܂��B���ɏ\���������C���N�Ŏx���������J�n���Ă��܂��B���{�͂��̂悤�ȍ��A�̗v���Ɋ�Â����a�v�������Ƃ��ĎQ��������̂ł��B����܂ł����A�̌��c���ɏ]���āA���q���̓J���{�W�A���͂��ߑ����̍���PKO�������s���Ă��܂����A9.11�e��������̓A�t�K�j�X�^���ւ��l�����������{���Ă��܂��B�C���N���������ۂ��闝�R������܂���B
�@�m���ɍ��̃C���N�͂܂��܂��댯���������Ƃ������ł��B�ł����獡�������q����h������̂ł͂Ȃ��A�\���Ȍ��n�������s���������Ŋ�{�v������肵�A���q���̔h�����߂���20���ȓ��ɍ���ɂ����F�����߂邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B����s���F�ł��������q���͊������I�����܂��B���{�Ƃ��ẮA���S���m���ł���n��Ǝ������m�F������Ŏ��q����h�����邱�Ƃ͓��R�ł��B
�@����}�ɂ��ẮA�u�}�����܂Ƃ߂��ꂸ�A�ꂵ����ɏC���Ă��o���A�̖ʂ����U�����ɂ����Ȃ��v(7.4�t�ǔ��V���А�)�B�܂��O�����S�ۏᐭ����߂���}���̈ӌ��Η��ƁA������܂Ƃߐ�Ȃ����s���̃��[�_�V�b�v�̌��@���I�悵���i�D�Łu����}�̖��ӔC�̎����\�ꂽ�v(7.2�t�Y�o�V��)�Ƌ��e����Ă��܂��B
�܂��u�l�E����e�F���������}�E�����}�v�Ȃǂƃf�}��`���s������̋��Y�}�c���́A���_�ʑ����̍߂ō��i����đR��ׂ��ł���ƍl���܂��B