竹内 譲
| 京都市基本構想について 「京都市基本構想」(いわゆるグランドビジョン)についてお伺い致します。私はこのグランドビジョンは京都の次 の100年の礎を築く誠に重大な基本構想であると考えています。枝葉末節にとらわれることなく、世界的、地球的視野で豊かな構想力をもって描いていくことが大事で |
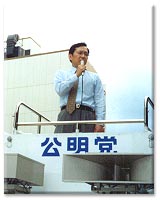 |
あると思います。
![]() その意味で台湾の李登輝総統が、最近の著書「台湾の主張」の中で日本の政治家に対して次のように述べておられることが大変示唆に富んでいます。
その意味で台湾の李登輝総統が、最近の著書「台湾の主張」の中で日本の政治家に対して次のように述べておられることが大変示唆に富んでいます。
![]() すなわち「政治家のレベルでいえば、部分的な細かなことには気がつくのだが、大局的な大枠の把握に欠けるようにみえる。なにかいつも、小手先のことばかり論じている。それはその政治家の能力がないからではなくて、信念あるいは自分に対する信頼感が欠落しているからなのである。政治家にかかわらず現在の日本人は、かつてなら精神的な修養といわれたような鍛練を行わなくなってしまった。私が日本思想から得た大きなものは、実はこうした精神的な鍛練の部分ではなかったかと思うのである。政治家はときとして能力と利害は無視できるようにならなければならない。そのためには「大きく太く」ものごとを把握しなければならない。政治家として必要なのは「大きく太く」ものごとを押さえる信念に裏打ちされた力である。日本の場合、明治維新後の留学生や政治家たちが外国の地に立ったときも、なんとか日本をよくしたいという信念をもっていたのである。」と。
すなわち「政治家のレベルでいえば、部分的な細かなことには気がつくのだが、大局的な大枠の把握に欠けるようにみえる。なにかいつも、小手先のことばかり論じている。それはその政治家の能力がないからではなくて、信念あるいは自分に対する信頼感が欠落しているからなのである。政治家にかかわらず現在の日本人は、かつてなら精神的な修養といわれたような鍛練を行わなくなってしまった。私が日本思想から得た大きなものは、実はこうした精神的な鍛練の部分ではなかったかと思うのである。政治家はときとして能力と利害は無視できるようにならなければならない。そのためには「大きく太く」ものごとを把握しなければならない。政治家として必要なのは「大きく太く」ものごとを押さえる信念に裏打ちされた力である。日本の場合、明治維新後の留学生や政治家たちが外国の地に立ったときも、なんとか日本をよくしたいという信念をもっていたのである。」と。
![]() 李登輝総統はかつて京都帝国大学農学部に学ばれ、京都には有縁の世界を代表する政治家であります。この総統の言葉は我々政治家がよく噛締めなければならないと思います。私は今回のグランドビジョンを策定するにあたっても、政治的駆け引きや浅薄な批判にたじろぐこと無く「大きく太く」、京都を良くしたいという「信念」をもって取り組まねばならないと考えますが、このような観点から市長の所感と決意を求めます。
李登輝総統はかつて京都帝国大学農学部に学ばれ、京都には有縁の世界を代表する政治家であります。この総統の言葉は我々政治家がよく噛締めなければならないと思います。私は今回のグランドビジョンを策定するにあたっても、政治的駆け引きや浅薄な批判にたじろぐこと無く「大きく太く」、京都を良くしたいという「信念」をもって取り組まねばならないと考えますが、このような観点から市長の所感と決意を求めます。
![]() (京都の歴史再考)
(京都の歴史再考)
![]() そこで、今回のグランドビジョンを考えるに当たってまず大事なことは、京都1200年の歴史を概括することによって京都の都市形成の本質をきちんと認識することです。このことによってこの都市の21世紀に通じる基本方針が見えてくるものと思われます。
そこで、今回のグランドビジョンを考えるに当たってまず大事なことは、京都1200年の歴史を概括することによって京都の都市形成の本質をきちんと認識することです。このことによってこの都市の21世紀に通じる基本方針が見えてくるものと思われます。
![]() (京都の都市形成の本質)
(京都の都市形成の本質)
![]() 京都の歴史を振り返ってみると、私は京都を形成させてきた基盤は、次のようにまとめることができると考えています。すなわち
京都の歴史を振り返ってみると、私は京都を形成させてきた基盤は、次のようにまとめることができると考えています。すなわち
![]() ①政治権力の中心地(政治首都)、
①政治権力の中心地(政治首都)、
![]() ②天皇の住む都市(皇都)
②天皇の住む都市(皇都)
![]() ③社会基盤形成と技術革新。の三つです。
③社会基盤形成と技術革新。の三つです。
![]() 仏教をはじめとする諸宗教、茶道・華道、陶芸、貴族文化、武家文化、西陣織物、京友禅など伝統文化と呼ばれるものは、ほとんど政治権力もしくは天皇家に由来しています。そして明治以降の近代化の中で京都を支えてきたものは、社会基盤形成と技術革新といえるでしょう。従って今後是非とも必要なことは、21世紀の社会基盤形成と技術革新です。とは言うものの明治維新以降今日に至るまで良きにつけ悪しきにつけ、京都はかつての政治首都もしくは皇都としての権力機構のもっていた遺産、すなわち「伝統」を引きずってきました。
仏教をはじめとする諸宗教、茶道・華道、陶芸、貴族文化、武家文化、西陣織物、京友禅など伝統文化と呼ばれるものは、ほとんど政治権力もしくは天皇家に由来しています。そして明治以降の近代化の中で京都を支えてきたものは、社会基盤形成と技術革新といえるでしょう。従って今後是非とも必要なことは、21世紀の社会基盤形成と技術革新です。とは言うものの明治維新以降今日に至るまで良きにつけ悪しきにつけ、京都はかつての政治首都もしくは皇都としての権力機構のもっていた遺産、すなわち「伝統」を引きずってきました。
![]() つまりそういう「伝統」を保存していこうとするのか、それとも「伝統」とは決別して「改革」の道をゆくのか、の選択の歴史でありました。明治遷都の時には「京都策」と呼ばれる近代化「改革」政策にウェイトを置いたと推定されます。たまたま太平洋戦争においては、京都が戦災から免れたことも手伝い、戦後はどちらかというと「伝統」の維持に重点が置かれたように見えます。しかしより正確に言うと、戦後の京都は自らの新しい独自性(アイデンティティ)を構築できないまま、「伝統」と「改革」の間を迷い揺れながら、結局総体としては「伝統」の維持以上に自らを乗り越えることはできなかったのではないでしょうか。
つまりそういう「伝統」を保存していこうとするのか、それとも「伝統」とは決別して「改革」の道をゆくのか、の選択の歴史でありました。明治遷都の時には「京都策」と呼ばれる近代化「改革」政策にウェイトを置いたと推定されます。たまたま太平洋戦争においては、京都が戦災から免れたことも手伝い、戦後はどちらかというと「伝統」の維持に重点が置かれたように見えます。しかしより正確に言うと、戦後の京都は自らの新しい独自性(アイデンティティ)を構築できないまま、「伝統」と「改革」の間を迷い揺れながら、結局総体としては「伝統」の維持以上に自らを乗り越えることはできなかったのではないでしょうか。
![]() (京都I・Tルネサンス構想)
(京都I・Tルネサンス構想)
![]() 私は21世紀の京都はもはや「伝統か改革か」ではなく、「伝統も改革も」必要であり、それらを超える次元での新しい独自性(アイデンティティ)が求められていると考えます。
私は21世紀の京都はもはや「伝統か改革か」ではなく、「伝統も改革も」必要であり、それらを超える次元での新しい独自性(アイデンティティ)が求められていると考えます。
![]() 今回のグランドビジョンではこの独自性(アイデンティティ)を明らかにする必要があり、かつそれは簡潔に表現できるものでなければなりません。そこで今回私の提唱する独自性(アイデンティティ)とは、「人を大切にするまち京都」です。それは同時に自然環境や有形・無形の文化財、景観、伝統の技あるいは美的感覚やくらしの智恵などを大事にすることでもあります。
今回のグランドビジョンではこの独自性(アイデンティティ)を明らかにする必要があり、かつそれは簡潔に表現できるものでなければなりません。そこで今回私の提唱する独自性(アイデンティティ)とは、「人を大切にするまち京都」です。それは同時に自然環境や有形・無形の文化財、景観、伝統の技あるいは美的感覚やくらしの智恵などを大事にすることでもあります。
![]() さらに今回のグランドビジョンにネーミングが必要と考えます。私はその題名を「京都I・Tルネサンス構想」と名づけてはどうかと提唱しております。「ルネサンス」とは14世紀から16世紀にかけてイタリアを中心に起った文芸復興運動ですが、それは同時に世界と人間の再発見、抑圧された自由な精神の復興を目的とした、人間性の尊重を求めるヒューマニズムの主張でもあったのです。その意味で「人を大切にするまち」作りを目指そうという構想には「ルネサンス」の呼び名がふさわしい。単に「人権の尊重」というにとどまらず、広くあらゆる分野にわたって「人を大切にする」という心遣いが溢れた都市にしたいと思います。そしてこの都市を復興していくために必要な技術革新として「情報技術」(I・T=Information
Technology)を位置づける。今、文化、産業、観光、学問、芸術、教育、環境、福祉などのすべての分野にわたって情報技術(I・T)革命が必要とされています。
さらに今回のグランドビジョンにネーミングが必要と考えます。私はその題名を「京都I・Tルネサンス構想」と名づけてはどうかと提唱しております。「ルネサンス」とは14世紀から16世紀にかけてイタリアを中心に起った文芸復興運動ですが、それは同時に世界と人間の再発見、抑圧された自由な精神の復興を目的とした、人間性の尊重を求めるヒューマニズムの主張でもあったのです。その意味で「人を大切にするまち」作りを目指そうという構想には「ルネサンス」の呼び名がふさわしい。単に「人権の尊重」というにとどまらず、広くあらゆる分野にわたって「人を大切にする」という心遣いが溢れた都市にしたいと思います。そしてこの都市を復興していくために必要な技術革新として「情報技術」(I・T=Information
Technology)を位置づける。今、文化、産業、観光、学問、芸術、教育、環境、福祉などのすべての分野にわたって情報技術(I・T)革命が必要とされています。
![]() このような意味でI・T(情報技術)革命によって、京都が景観や環境を守りながら、21世紀に大きく復興し再生するチャンスが広がっていると言えるでしょう。「京都I・Tルネサンス構想」と命名する所以です。以上の見解にもとづき私は、この7月パブリックコメントとして、京都市に対しまして「私の京都21世紀グランドビジョン~京都I・Tルネサンス構想」を提出致しました。これは私のホームページでも公開しています。さらに公明党では既に「京都市基本構想第一次提言」を提出しておりますが、これらに対しまして起草委員会ではどのような議論がなされたかをお尋ね致します。
このような意味でI・T(情報技術)革命によって、京都が景観や環境を守りながら、21世紀に大きく復興し再生するチャンスが広がっていると言えるでしょう。「京都I・Tルネサンス構想」と命名する所以です。以上の見解にもとづき私は、この7月パブリックコメントとして、京都市に対しまして「私の京都21世紀グランドビジョン~京都I・Tルネサンス構想」を提出致しました。これは私のホームページでも公開しています。さらに公明党では既に「京都市基本構想第一次提言」を提出しておりますが、これらに対しまして起草委員会ではどのような議論がなされたかをお尋ね致します。
京都市の産業政策について
![]() (問題意識)
(問題意識)
![]() 次に京都市の産業政策についてお伺い致します。私は京都市のグランドビジョンを実行するためには産業政策こそがもっとも大事であると考えます。なぜなら、産業がなければ140万人を超える京都市民の暮らしを支え、福祉を充実していくことは困難であるからです。京都市では平成7年に「ものづくり都市京都」を理念とした「京都市産業振興ビジョン」をまとめておられます。私はこれは概ね正しい方向であると考えますが、ここ数年の著しい情報技術の進展によって、世界経済全体が大変動を起こしております。ある学者は「21世紀の産業はただ一つ。情報産業だけになる。売るのはモノではなく、サービスだ。高付加価値の企業体質を作るには製造業の進化が必要だ。」と言い切っています。
次に京都市の産業政策についてお伺い致します。私は京都市のグランドビジョンを実行するためには産業政策こそがもっとも大事であると考えます。なぜなら、産業がなければ140万人を超える京都市民の暮らしを支え、福祉を充実していくことは困難であるからです。京都市では平成7年に「ものづくり都市京都」を理念とした「京都市産業振興ビジョン」をまとめておられます。私はこれは概ね正しい方向であると考えますが、ここ数年の著しい情報技術の進展によって、世界経済全体が大変動を起こしております。ある学者は「21世紀の産業はただ一つ。情報産業だけになる。売るのはモノではなく、サービスだ。高付加価値の企業体質を作るには製造業の進化が必要だ。」と言い切っています。
![]() この8月私は関西生産性本部の夏季研修会に参加致しました。そこではオムロンの立石社長、ロームや京セラを始めとして関西を代表する産業界や大学の一流の学者の先生方によって、「関西に如何にして新産業を創出するか」について熱心な討論がなされました。研修会での議論は、「今世界の産業構造が変化しているにもかかわらず、日本が気がついていない。80年代日本の産業界がジャパン・アズ・ナンバーワンと称し、もうアメリカに学ぶものは無くなったと豪語していた時に、アメリカでは大変な危機感から日本の成功の原因を徹底的に調査・分析した上で、自らの産業形態の変革に取り組み、もの作りのレベルでは日本に譲歩し油断させながら、一番付加価値の高い部分はアメリカが握ってしまうという世界戦略を打ってきた。これが現在のアメリカの繁栄につながっている」というものでした。私はこのような世界情勢の変化に鑑み、これまでの京都市産業振興ビジョンの「ものづくり都市」の概念に加えて、新たな発想に基づいた戦略が必要であると考えます。
この8月私は関西生産性本部の夏季研修会に参加致しました。そこではオムロンの立石社長、ロームや京セラを始めとして関西を代表する産業界や大学の一流の学者の先生方によって、「関西に如何にして新産業を創出するか」について熱心な討論がなされました。研修会での議論は、「今世界の産業構造が変化しているにもかかわらず、日本が気がついていない。80年代日本の産業界がジャパン・アズ・ナンバーワンと称し、もうアメリカに学ぶものは無くなったと豪語していた時に、アメリカでは大変な危機感から日本の成功の原因を徹底的に調査・分析した上で、自らの産業形態の変革に取り組み、もの作りのレベルでは日本に譲歩し油断させながら、一番付加価値の高い部分はアメリカが握ってしまうという世界戦略を打ってきた。これが現在のアメリカの繁栄につながっている」というものでした。私はこのような世界情勢の変化に鑑み、これまでの京都市産業振興ビジョンの「ものづくり都市」の概念に加えて、新たな発想に基づいた戦略が必要であると考えます。
![]() (世界経済の大状況と日本経済)
(世界経済の大状況と日本経済)
![]() そこでまず近年の世界経済の動きについて観ておきたいと思います。バブル崩壊後の日本経済はまったくといって良いほど低迷しています。これに対して政府は公共工事と減税を中心とした従来型の経済政策を中心に対応して参りましたが、一定の効果を認めつつも公債残高の累増から早晩限界を迎えることになるでしょう。日本経済停滞の原因を考えるには、まず世界経済の環境変化ということを理解する必要があります。
そこでまず近年の世界経済の動きについて観ておきたいと思います。バブル崩壊後の日本経済はまったくといって良いほど低迷しています。これに対して政府は公共工事と減税を中心とした従来型の経済政策を中心に対応して参りましたが、一定の効果を認めつつも公債残高の累増から早晩限界を迎えることになるでしょう。日本経済停滞の原因を考えるには、まず世界経済の環境変化ということを理解する必要があります。
![]() この点について京都大学経済学部教授の下谷政弘先生は概ね次のように指摘されています。「こうした状況に陥ったのには、国際的な経済環境の変化が及ぼした影響を無視できない。すなわちグローバル競争あるいはメガ・コンペティション(大競争)といわれる新時代へのシフトである。80年代末からの東欧やソ連などの社会主義経済体制の挫折は衝撃的であった。これまでの資本主義(市場)経済と社会主義(計画)経済という対立は終わりを告げ、中国も社会主義的市場経済の方向へと舵を切替えた。
この点について京都大学経済学部教授の下谷政弘先生は概ね次のように指摘されています。「こうした状況に陥ったのには、国際的な経済環境の変化が及ぼした影響を無視できない。すなわちグローバル競争あるいはメガ・コンペティション(大競争)といわれる新時代へのシフトである。80年代末からの東欧やソ連などの社会主義経済体制の挫折は衝撃的であった。これまでの資本主義(市場)経済と社会主義(計画)経済という対立は終わりを告げ、中国も社会主義的市場経済の方向へと舵を切替えた。
![]() つまり、世界経済全体が資本主義的な市場経済へと転換し始めた。市場経済は競争原理を基本としている。従って各国それぞれの市場経済システムのあり方が、その国の国際競争力を規定するという時代を迎えたのである。これは国ごとのいわゆる『システム間競争』である。こうした激しい国際競争の波が旧来の日本経済のシステム変更を迫っている。また、近年の情報技術の急速な進歩が世界経済のあり方を根本的に変革してしまった。世界経済はますますその変化の速度を高めており、そのスピードが、これまで半世紀にわたり日本経済の発展を支えてきた日本型システムを一気に陳腐なものに一変させたのである」と。
つまり、世界経済全体が資本主義的な市場経済へと転換し始めた。市場経済は競争原理を基本としている。従って各国それぞれの市場経済システムのあり方が、その国の国際競争力を規定するという時代を迎えたのである。これは国ごとのいわゆる『システム間競争』である。こうした激しい国際競争の波が旧来の日本経済のシステム変更を迫っている。また、近年の情報技術の急速な進歩が世界経済のあり方を根本的に変革してしまった。世界経済はますますその変化の速度を高めており、そのスピードが、これまで半世紀にわたり日本経済の発展を支えてきた日本型システムを一気に陳腐なものに一変させたのである」と。
![]() (情報革命とは何か)
(情報革命とは何か)
したがって私はこの不況を脱するには小手先の経済対策では駄目であり、日本経済の抜本的な構造改革を必要とします。京都の21世紀の産業政策を立案する場合にもこのような世界的な大状況に対する認識が不可欠と言えるでしょう。そしてその中でも特に情報革命を京都の再興に役立てることが大事です。
![]() アメリカ商務省のレポート「デジタル・エコノミー」は次のように述べています。「近年アメリカ経済は、ほとんど誰もが予期しなかった繁栄を続けている。連邦準備理事会議長のグリーンスパン氏は『こうした好業績はコンピューターや通信の驚くべき性能向上と情報技術によってもたらされたように見える』と述べている。」三和総合研究所の調査によると、「アメリカの91年から98年の雇用者増加1,800万人のうち600万人は情報化の進展による雇用創出である。」と報告されています。そしてアメリカ商務省レポートでは、「このようにして創り出された何百万もの新しい職は高度な熟練と高給が特徴的である。ここでの挑戦課題は、現在と将来の労働力がこうした新職業に就けるよう準備をしておくこと。デジタルエコノミーの仕事に必要な技能を学生や労働者に教えられる人材の育成などを進めていかねばならない」。と指摘しています。
アメリカ商務省のレポート「デジタル・エコノミー」は次のように述べています。「近年アメリカ経済は、ほとんど誰もが予期しなかった繁栄を続けている。連邦準備理事会議長のグリーンスパン氏は『こうした好業績はコンピューターや通信の驚くべき性能向上と情報技術によってもたらされたように見える』と述べている。」三和総合研究所の調査によると、「アメリカの91年から98年の雇用者増加1,800万人のうち600万人は情報化の進展による雇用創出である。」と報告されています。そしてアメリカ商務省レポートでは、「このようにして創り出された何百万もの新しい職は高度な熟練と高給が特徴的である。ここでの挑戦課題は、現在と将来の労働力がこうした新職業に就けるよう準備をしておくこと。デジタルエコノミーの仕事に必要な技能を学生や労働者に教えられる人材の育成などを進めていかねばならない」。と指摘しています。
![]() 私は京都のような地方政府が掲げる産業政策の中では、この点が大変重要ではないかと考えています。これはまさに教育の問題でもあるわけです。具体的な政策提言に移る前にまず現状の京都経済の総括と産業政策の問題点を明らかにする必要があります。
私は京都のような地方政府が掲げる産業政策の中では、この点が大変重要ではないかと考えています。これはまさに教育の問題でもあるわけです。具体的な政策提言に移る前にまず現状の京都経済の総括と産業政策の問題点を明らかにする必要があります。
![]() (80年代以降の京都経済)
(80年代以降の京都経済)
![]() 京都市産業振興ビジョンによると、「80年代以降の京都市の経済成長力は全国や首都圏・関西圏の大都市と比べて劣っている。その大きな要因のひとつは、製造業の成長寄与度の低下。その中でも繊維産業の集積規模の低下が最大であり、それ以外の産業についても全国同業種との比較では成長性は低いものとなっている。また、ものづくりの基盤が揺らいでいることも大きな要因。そのひとつは人や大学・企業の市外流出である。また産業創造力の弱体化である。」などを指摘しつつ、総括として「産業面では和装産業の一大拠点であるという以外には、中枢的な地位を次第に失っていった。全国的あるいは世界的に見て、京都市が産業分野の先端的な交流センターとしては機能していない。このような状況の変化は、京都市のものづくりの自己革新力を弱めている。しかも、京都市のものづくり基盤が揺らいでいることを考え合わせると、このままでは新規展開の活力は急速に失われる懸念がある」と大変な危機感を訴えているのです。
京都市産業振興ビジョンによると、「80年代以降の京都市の経済成長力は全国や首都圏・関西圏の大都市と比べて劣っている。その大きな要因のひとつは、製造業の成長寄与度の低下。その中でも繊維産業の集積規模の低下が最大であり、それ以外の産業についても全国同業種との比較では成長性は低いものとなっている。また、ものづくりの基盤が揺らいでいることも大きな要因。そのひとつは人や大学・企業の市外流出である。また産業創造力の弱体化である。」などを指摘しつつ、総括として「産業面では和装産業の一大拠点であるという以外には、中枢的な地位を次第に失っていった。全国的あるいは世界的に見て、京都市が産業分野の先端的な交流センターとしては機能していない。このような状況の変化は、京都市のものづくりの自己革新力を弱めている。しかも、京都市のものづくり基盤が揺らいでいることを考え合わせると、このままでは新規展開の活力は急速に失われる懸念がある」と大変な危機感を訴えているのです。
![]() (ビジョンの評価と問題点)
(ビジョンの評価と問題点)
京都の産業低迷について当時としては的確な分析がなされ、原因の指摘については概ね正鵠を射ているものと思われます。しかし以下のような点について問題点があると考えます。
![]() ①インターネットをはじめ、近年の情報技術の飛躍的発展を踏まえて、それを産
①インターネットをはじめ、近年の情報技術の飛躍的発展を踏まえて、それを産![]() 業政策の中にどのように活かしていくのかについて検討する必要があります。
業政策の中にどのように活かしていくのかについて検討する必要があります。
![]() ②「ものづくり都市」の理念に加えて、今後の産業政策のもう一つの柱として、
②「ものづくり都市」の理念に加えて、今後の産業政策のもう一つの柱として、![]() 「知識創造型」産業の育成を大胆に打ち出すことも必要です。
「知識創造型」産業の育成を大胆に打ち出すことも必要です。
![]() ③高度な産学連携だけでなく、中小企業の技術革新を促す必要があります。
③高度な産学連携だけでなく、中小企業の技術革新を促す必要があります。
![]() ④実践編の中では政策の動機づけ(インセンティブ)こそがもっとも大事であり、
④実践編の中では政策の動機づけ(インセンティブ)こそがもっとも大事であり、![]() この点を詰める必要があります。
この点を詰める必要があります。
![]() ⑤米国のシリコンバレーなどをモデルにした京都リサーチパークの設立や新産
⑤米国のシリコンバレーなどをモデルにした京都リサーチパークの設立や新産
![]() 業創出のためのプラットフォーム構想、またベンチャー企業メキキ委員会の
業創出のためのプラットフォーム構想、またベンチャー企業メキキ委員会の
![]() 発足、デジタルアーカイブ事業などは評価できますが、80年代のように箱物
発足、デジタルアーカイブ事業などは評価できますが、80年代のように箱物
![]() を用意すれば産業集積ができるという考え方に陥らないようにする必要があ
を用意すれば産業集積ができるという考え方に陥らないようにする必要があ
![]() ります。時代はますます速いスピードで動いています。各自治体も情報産業の
ります。時代はますます速いスピードで動いています。各自治体も情報産業の![]() 集積に力をいれてきましたが、期待外れの地域が多くあります。
集積に力をいれてきましたが、期待外れの地域が多くあります。
![]() ⑥全体として、京都の魅力を高めるための起爆剤が無いということです。交流
⑥全体として、京都の魅力を高めるための起爆剤が無いということです。交流
![]() や人材育成を通じて外部との接触を高め、産業の新陳代謝を促すエネルギ
や人材育成を通じて外部との接触を高め、産業の新陳代謝を促すエネルギ
![]() ーを創り出す積極的な仕掛けという点で、中核となる起爆剤的プロジェクトが
ーを創り出す積極的な仕掛けという点で、中核となる起爆剤的プロジェクトが
![]() 欠落していることです。このままでは資金と労力を使う割には効果が無いと
欠落していることです。このままでは資金と労力を使う割には効果が無いと
![]() いうことになりかねません。
いうことになりかねません。
![]() (具体的提言)
(具体的提言)
以上のような分析を踏まえた上で、私は今後新たに策定される21世紀の京都の産業政策について次のような具体的提言を致したいと思います。
![]() (知識創造都市をめざす)
(知識創造都市をめざす)
![]() まず第一の点は、これまでの「ものづくり都市」の理念に加えて「知識創造都市」をめざすという理念が必要であると考えています。この「知識創造」という意味は経営学の分野では深い意味がありますが、ここでは「個々の断片的な情報やデータという概念ではなく、情報やデータを関係づけ編集することにより新しい知識を生み出す過程」のことです。産業としては教育産業、マルチメディア・コンテンツ産業、デザイン・グラフィック産業」、また環境技術産業、バイオ・医療産業等の新しい産業形態が想定されます。情報革命時代における「メガ・コンペティションのもとでは、市場はもはや国内市場ではなくグローバル市場としての性格を帯び、世界的にみて個性化、差別化された商品・サービスでなければ競争力を有することができなくなり、(ハーバード大学教授の)マイケル・ポーター氏のいう世界のすきま(グローバル・ニッチ)をめざすことが企業の目標」となるでしょう。さらに「このようなグローバリゼーションの中で今後は地域が主役になる」可能性が高いといえます。なぜならそのような「世界的に唯一といえる商品・サービスを供給するためには国よりも細分化された地域における情報内容(コンテンツ)が国際競争力の基本となるからです。」その意味で、西洋文化と対局にある「感性を重視し自然との共生を基本とする東洋、特に日本」その中でも京都は「情報化社会において大きく発展していく」可能性があるのです。したがって京都において「マルチメディアのコンテンツを開発する感性豊な人材」の輩出が重要になるでありましょう。
まず第一の点は、これまでの「ものづくり都市」の理念に加えて「知識創造都市」をめざすという理念が必要であると考えています。この「知識創造」という意味は経営学の分野では深い意味がありますが、ここでは「個々の断片的な情報やデータという概念ではなく、情報やデータを関係づけ編集することにより新しい知識を生み出す過程」のことです。産業としては教育産業、マルチメディア・コンテンツ産業、デザイン・グラフィック産業」、また環境技術産業、バイオ・医療産業等の新しい産業形態が想定されます。情報革命時代における「メガ・コンペティションのもとでは、市場はもはや国内市場ではなくグローバル市場としての性格を帯び、世界的にみて個性化、差別化された商品・サービスでなければ競争力を有することができなくなり、(ハーバード大学教授の)マイケル・ポーター氏のいう世界のすきま(グローバル・ニッチ)をめざすことが企業の目標」となるでしょう。さらに「このようなグローバリゼーションの中で今後は地域が主役になる」可能性が高いといえます。なぜならそのような「世界的に唯一といえる商品・サービスを供給するためには国よりも細分化された地域における情報内容(コンテンツ)が国際競争力の基本となるからです。」その意味で、西洋文化と対局にある「感性を重視し自然との共生を基本とする東洋、特に日本」その中でも京都は「情報化社会において大きく発展していく」可能性があるのです。したがって京都において「マルチメディアのコンテンツを開発する感性豊な人材」の輩出が重要になるでありましょう。
![]() (日本型ビジネススクールの設立)
(日本型ビジネススクールの設立)
![]() 二番目の提言は、21世紀の京都の起爆剤として、情報革命に対応でき、若い才能を引き付ける魅力ある「日本型ビジネススクール」の設立です。アメリカのビジネススクールは1881年のペンシルバニア大学ウォートン校にその原形が開設されて以来今日に至るまで長い歴史を誇っています。アメリカ経済の発展は、経営学修士(MBA)に象徴されるビジネススクールとともにあるといわれるほどその影響力は大きなものがあります。スタンフォード大学やMITのビジネススクールでは校内の研究者のアイデアや発明を実際のビジネスにつなげてベンチャー企業を立ち上げるという実践の場にビジネススクールが貢献しています。今日までにMITが立ち上げた地元ビジネスは640社にのぼるとされており、シリコンバレーがスタンフォード大学を核として発展していったことは有名です。
二番目の提言は、21世紀の京都の起爆剤として、情報革命に対応でき、若い才能を引き付ける魅力ある「日本型ビジネススクール」の設立です。アメリカのビジネススクールは1881年のペンシルバニア大学ウォートン校にその原形が開設されて以来今日に至るまで長い歴史を誇っています。アメリカ経済の発展は、経営学修士(MBA)に象徴されるビジネススクールとともにあるといわれるほどその影響力は大きなものがあります。スタンフォード大学やMITのビジネススクールでは校内の研究者のアイデアや発明を実際のビジネスにつなげてベンチャー企業を立ち上げるという実践の場にビジネススクールが貢献しています。今日までにMITが立ち上げた地元ビジネスは640社にのぼるとされており、シリコンバレーがスタンフォード大学を核として発展していったことは有名です。
![]() 日本の文部省はこの9月に専門性の高い職業人の育成に目的を絞った「専門大学院」の開設を可能にする文部省令の改正を行うことになりました。これを受けて、一橋大学では大学院に「国際企業戦略研究科」の新設を準備中です。これは東京千代田区のビルを拠点に「法務・公共政策専攻」、「経営・金融専攻」などの講座を開き、アジアからの留学生の受け入れも視野にすべて英語で授業を行うもので、アメリカのビジネススクール型といえるでしょう。京都大学でも公衆衛生のプロを育てる専門大学院の設置を予定しています。
日本の文部省はこの9月に専門性の高い職業人の育成に目的を絞った「専門大学院」の開設を可能にする文部省令の改正を行うことになりました。これを受けて、一橋大学では大学院に「国際企業戦略研究科」の新設を準備中です。これは東京千代田区のビルを拠点に「法務・公共政策専攻」、「経営・金融専攻」などの講座を開き、アジアからの留学生の受け入れも視野にすべて英語で授業を行うもので、アメリカのビジネススクール型といえるでしょう。京都大学でも公衆衛生のプロを育てる専門大学院の設置を予定しています。
![]() 大阪では大阪電気通信大学が、学部段階ですが、ゲーム会社のコナミと提携し2000年4月にメディア情報文化学科を開設されます。デジタルメディア社会の到来を予測して、メディアデザイン、メディアアート、メディアコミュニケーションなどのコースを用意し、将来Webデザイナー・アートディレクター、サウンドクリエイター・音楽プロデューサー、マスコミスタッフ・ビデオジャーナリスト、ゲームクリエイターなどを目指す人材養成を行うものです。映画監督の大森一樹氏や現役のゲームクリエイターなどが直接指導します。同時に哲学・芸術・異文化理解・法律・経済・英語・中国語・韓国語・福祉なども総合的に教育するシステムになっています。またこれは専修学校ですが、大阪でマルチメディアの人材育成機関「インターメディウム研究所(IMI)が設立されました。これは若者から見て魅力のない地域は衰退の道を歩むのではないか、との危機感から創立されたものです。
大阪では大阪電気通信大学が、学部段階ですが、ゲーム会社のコナミと提携し2000年4月にメディア情報文化学科を開設されます。デジタルメディア社会の到来を予測して、メディアデザイン、メディアアート、メディアコミュニケーションなどのコースを用意し、将来Webデザイナー・アートディレクター、サウンドクリエイター・音楽プロデューサー、マスコミスタッフ・ビデオジャーナリスト、ゲームクリエイターなどを目指す人材養成を行うものです。映画監督の大森一樹氏や現役のゲームクリエイターなどが直接指導します。同時に哲学・芸術・異文化理解・法律・経済・英語・中国語・韓国語・福祉なども総合的に教育するシステムになっています。またこれは専修学校ですが、大阪でマルチメディアの人材育成機関「インターメディウム研究所(IMI)が設立されました。これは若者から見て魅力のない地域は衰退の道を歩むのではないか、との危機感から創立されたものです。
![]() このIMIのゼネラルマネージャーで、出資母体の一つである成安造形大学の畑祥雄助教授は次のように述べています。「緒方洪庵が江戸末期に開いた適塾では、若い才能が蘭学を学ぶために一冊の辞書を奪い合うようにして知力を磨いた。その中から福沢諭吉が文明論の概略を創造力豊かに著わした。洋学を学ぶことによって蓄えられた知力と創造力が組み合わさったパワーは、貪欲に紡績などの技術を吸収し、やがて大阪が東洋のマンチェスターとまで呼ばれるまでに発展する原動力となった。いつの時代も若い才能が集まるところに、知力と創造力と技術力がみなぎる」と。大変刺激的であり参考になる事例であると思います。
このIMIのゼネラルマネージャーで、出資母体の一つである成安造形大学の畑祥雄助教授は次のように述べています。「緒方洪庵が江戸末期に開いた適塾では、若い才能が蘭学を学ぶために一冊の辞書を奪い合うようにして知力を磨いた。その中から福沢諭吉が文明論の概略を創造力豊かに著わした。洋学を学ぶことによって蓄えられた知力と創造力が組み合わさったパワーは、貪欲に紡績などの技術を吸収し、やがて大阪が東洋のマンチェスターとまで呼ばれるまでに発展する原動力となった。いつの時代も若い才能が集まるところに、知力と創造力と技術力がみなぎる」と。大変刺激的であり参考になる事例であると思います。
![]() 私の提唱する「日本型ビジネススクール」は、法的にはまず文部省の言う高度の専門職業人を養成する専門大学院を想定しています。専門の分野としては、経営管理、法律実務、ファイナンス、国際開発・協力、公共政策、公衆衛生などが考えられています。しかし、現在情報家電時代の到来を予測し、21世紀のエレクトロニクス産業を支える大規模集積回路(システムLSI)を最終製品に組み込んで使用するための半導体設計資産(システムLSI
IP)の開発競争が欧米と日本との間で激しく繰り広げられています。ところが、このシステム設計ができる人材は現在の日本の産業界には構造的に欠乏しています。産業界は今のところ京都大学や大阪大学の大学院を通して現役の大学院生に設計を委託しているような実状です。しかしこの半導体設計資産の開発の優劣が21世紀の日本産業の生死を握っていると言っても過言ではありません。またバイオなど生命科学の分野でも同様の世界的な競争が行われています。環境技術と合わせて今後これらの分野で大学院生の研究開発の知力や腕力の必要性がますます増大していくと思われます。
私の提唱する「日本型ビジネススクール」は、法的にはまず文部省の言う高度の専門職業人を養成する専門大学院を想定しています。専門の分野としては、経営管理、法律実務、ファイナンス、国際開発・協力、公共政策、公衆衛生などが考えられています。しかし、現在情報家電時代の到来を予測し、21世紀のエレクトロニクス産業を支える大規模集積回路(システムLSI)を最終製品に組み込んで使用するための半導体設計資産(システムLSI
IP)の開発競争が欧米と日本との間で激しく繰り広げられています。ところが、このシステム設計ができる人材は現在の日本の産業界には構造的に欠乏しています。産業界は今のところ京都大学や大阪大学の大学院を通して現役の大学院生に設計を委託しているような実状です。しかしこの半導体設計資産の開発の優劣が21世紀の日本産業の生死を握っていると言っても過言ではありません。またバイオなど生命科学の分野でも同様の世界的な競争が行われています。環境技術と合わせて今後これらの分野で大学院生の研究開発の知力や腕力の必要性がますます増大していくと思われます。
![]() そこで将来京都に「日本型ビジネススクール」である専門大学院を核として、情報・バイオ・環境などの大学院やマルチメディアの人材育成機関、民間シンクタンクなども合わせて誘致し、いわば「知識創造の複合施設(ナレッジ・クリエイティング・コンプレックス)」を設立することを提唱致します。この「知識創造の複合施設」は、例えば上京区・中京区・下京区の小学校跡地いくつかを京都市が提供し、加えて企業や市民も智恵や資金を出して創設してはどうでしょうか。大学を他都市にとられて嘆く前に、土地や建物を気前良く提供し、また最高の通信インフラを整備して、日本中や世界から大学院や研究所を誘致するあるいはみずから設立するくらいの覇気が必要です。経営は国内のみならず全世界から公募するという方式も考えられるでしょう。スタンフォード大学やMITなど世界の一流大学と提携することも当然ありえます。起業家学校や起業家塾というのも結構ですが、起爆剤としては京都市が「日本型ビジネススクール」設立に乗り出したという方が、魅力があり世界から人が集まり、地域開発の点でも効果があると考えます。また「ものづくり」の伝統がある京都はこのような「日本型ビジネススクール」における「知識創造」が、「ものづくり」へと活かせる極めて可能性のある都市であると言えるのではないでしょうか。
そこで将来京都に「日本型ビジネススクール」である専門大学院を核として、情報・バイオ・環境などの大学院やマルチメディアの人材育成機関、民間シンクタンクなども合わせて誘致し、いわば「知識創造の複合施設(ナレッジ・クリエイティング・コンプレックス)」を設立することを提唱致します。この「知識創造の複合施設」は、例えば上京区・中京区・下京区の小学校跡地いくつかを京都市が提供し、加えて企業や市民も智恵や資金を出して創設してはどうでしょうか。大学を他都市にとられて嘆く前に、土地や建物を気前良く提供し、また最高の通信インフラを整備して、日本中や世界から大学院や研究所を誘致するあるいはみずから設立するくらいの覇気が必要です。経営は国内のみならず全世界から公募するという方式も考えられるでしょう。スタンフォード大学やMITなど世界の一流大学と提携することも当然ありえます。起業家学校や起業家塾というのも結構ですが、起爆剤としては京都市が「日本型ビジネススクール」設立に乗り出したという方が、魅力があり世界から人が集まり、地域開発の点でも効果があると考えます。また「ものづくり」の伝統がある京都はこのような「日本型ビジネススクール」における「知識創造」が、「ものづくり」へと活かせる極めて可能性のある都市であると言えるのではないでしょうか。
![]() (新産業創出優良賃貸オフィス制度の創設)
(新産業創出優良賃貸オフィス制度の創設)
![]() 第三の提言はこのような知識創造型企業の集積のための条件についてです。富士通総合研究所の湯川
抗氏の調査によれば、「先進国では知識集約型の産業構造へと転換を図るために米国のシリコンバレーが代表的なものとして取り上げられてきたが、近年米国各地においてシリコンバレーのような技術開発型の情報産業だけでなく、文化創造を伴うコンテンツ産業の集積地域が主に大都市中心部において生れ始めている。」
その典型がニューヨーク市の「シリコンアレー」と呼ばれるマンハッタン南部地域であり、またサンフランシスコ市の「マルチメディアガルチ」と呼ばれる一帯です。そしてこれらの諸都市を視察した結果、ネットビジネスの集積の条件は「高いソーシャルアメニティ(社会的快適さ)、安価なスペース、アーティスト(芸術家や音楽家など)の集積、関連教育機関、の四点」である。
第三の提言はこのような知識創造型企業の集積のための条件についてです。富士通総合研究所の湯川
抗氏の調査によれば、「先進国では知識集約型の産業構造へと転換を図るために米国のシリコンバレーが代表的なものとして取り上げられてきたが、近年米国各地においてシリコンバレーのような技術開発型の情報産業だけでなく、文化創造を伴うコンテンツ産業の集積地域が主に大都市中心部において生れ始めている。」
その典型がニューヨーク市の「シリコンアレー」と呼ばれるマンハッタン南部地域であり、またサンフランシスコ市の「マルチメディアガルチ」と呼ばれる一帯です。そしてこれらの諸都市を視察した結果、ネットビジネスの集積の条件は「高いソーシャルアメニティ(社会的快適さ)、安価なスペース、アーティスト(芸術家や音楽家など)の集積、関連教育機関、の四点」である。
![]() そしてわが国でコンテンツ産業を振興していくには現在のポテンシャルの高い地域を集中的に支援していくことが有効であり、その有望地域の条件は端的に言えば、『文化的水準の高い大都市である』。」として京都を挙げられていいます。
既に述べて参りました「日本型ビジネススクール」構想はこの中の関連教育機関に相当すると言えます。 95年にニューヨーク市が実行した「マンハッタン南部経済活性化計画(Lower
Manhattan Plan)は「低迷するダウンタウンに環境を整備して新産業を育成し、雇用を創出すると共に、住環境も整備することでニューヨーク市全体に資金が還流し、活性化させる」ことを目的とし、「ダウンタウンに移転した企業(企業の規模や業種を問わず)に対して一定の経済的なインセンティブ」を与えています。例えば固定資産税や電気料金の減免。また広告やマーケティングなどのサポートや資金援助。あるいは企業交流の組織作りを推進しています。
そしてわが国でコンテンツ産業を振興していくには現在のポテンシャルの高い地域を集中的に支援していくことが有効であり、その有望地域の条件は端的に言えば、『文化的水準の高い大都市である』。」として京都を挙げられていいます。
既に述べて参りました「日本型ビジネススクール」構想はこの中の関連教育機関に相当すると言えます。 95年にニューヨーク市が実行した「マンハッタン南部経済活性化計画(Lower
Manhattan Plan)は「低迷するダウンタウンに環境を整備して新産業を育成し、雇用を創出すると共に、住環境も整備することでニューヨーク市全体に資金が還流し、活性化させる」ことを目的とし、「ダウンタウンに移転した企業(企業の規模や業種を問わず)に対して一定の経済的なインセンティブ」を与えています。例えば固定資産税や電気料金の減免。また広告やマーケティングなどのサポートや資金援助。あるいは企業交流の組織作りを推進しています。
![]() このような分析からすると、従来のような京都は南部開発しそこへ新産業を集積するという計画は進める必要はあるけれども、マルチメディアコンテンツなどの知識創造型産業については、ソーシャルアメニティや文化的水準の高い旧市街地を活用するという考え方もありうるのではないでしょうか。
例えば西陣などの京都の町屋を活用して新規事業を起こす場合や、あるいは不良債権化したビルや工場を買い取って、新たに市内中心部に新産業を集積するため通信インフラの整備されたオフィスビルを建設する場合には、建設資金の融資の優遇制度や補助金の交付、固定資産税や電気料金の減免などのインセンティブを与えることを提案致します。
そしてこのような受益を得た場合にはテナントの賃貸料を安くしなければならないと定めるのです。これを「新産業創出優良賃貸オフィス」制度とでも名づけてはどうでしょうか。
このような分析からすると、従来のような京都は南部開発しそこへ新産業を集積するという計画は進める必要はあるけれども、マルチメディアコンテンツなどの知識創造型産業については、ソーシャルアメニティや文化的水準の高い旧市街地を活用するという考え方もありうるのではないでしょうか。
例えば西陣などの京都の町屋を活用して新規事業を起こす場合や、あるいは不良債権化したビルや工場を買い取って、新たに市内中心部に新産業を集積するため通信インフラの整備されたオフィスビルを建設する場合には、建設資金の融資の優遇制度や補助金の交付、固定資産税や電気料金の減免などのインセンティブを与えることを提案致します。
そしてこのような受益を得た場合にはテナントの賃貸料を安くしなければならないと定めるのです。これを「新産業創出優良賃貸オフィス」制度とでも名づけてはどうでしょうか。
![]() (京都版「中小企業技術革新制度」の創設)
(京都版「中小企業技術革新制度」の創設)
![]() 第四番目の提言は中小企業の技術革新を促進することです。ひとつの事例を紹介したいと思います。西陣紋様同志会ではここ数年の急激な受注量の減少によって、このままではもはや事業が成り立ちゆかなくなるとの強い危機感から、今回インターネットをはじめとする情報技術の導入によって企業経営の革新を行うために「西陣紋様同志会情報ネットワーク構想」をまとめられました。
それは西陣誕生以来継承されてきた伝統的紋様技術と、近年開発されてきた高度な画像処理能力を融合することによって、今日まで築かれて磨きあげられてきた「日本のデザイン」を「ニュージャポネスク」として多方面にわたる世界のデザイン市場に対し迅速に発信するための調査研究です。報告書では「本事業は西陣産地にあって受注生産という受動的形態の枠組みから一歩を踏み出し、市場を世界に広げることによって、閉鎖状態にあるわが業界の活性化の突破口となることを確信するものである。」と述べられています。
西陣紋様同志会ではこの9月から組合員向けの勉強会を連続して行うそうです。私は本構想は情報技術によって伝統産業を復興していくモデルになるものと高く評価しています。今回の西陣紋様同志会の調査研究では京都府立大学の応援を得ているのですが、京都市としてもこのような中小企業の産学連携と技術革新を支援していくことが求められています。
第四番目の提言は中小企業の技術革新を促進することです。ひとつの事例を紹介したいと思います。西陣紋様同志会ではここ数年の急激な受注量の減少によって、このままではもはや事業が成り立ちゆかなくなるとの強い危機感から、今回インターネットをはじめとする情報技術の導入によって企業経営の革新を行うために「西陣紋様同志会情報ネットワーク構想」をまとめられました。
それは西陣誕生以来継承されてきた伝統的紋様技術と、近年開発されてきた高度な画像処理能力を融合することによって、今日まで築かれて磨きあげられてきた「日本のデザイン」を「ニュージャポネスク」として多方面にわたる世界のデザイン市場に対し迅速に発信するための調査研究です。報告書では「本事業は西陣産地にあって受注生産という受動的形態の枠組みから一歩を踏み出し、市場を世界に広げることによって、閉鎖状態にあるわが業界の活性化の突破口となることを確信するものである。」と述べられています。
西陣紋様同志会ではこの9月から組合員向けの勉強会を連続して行うそうです。私は本構想は情報技術によって伝統産業を復興していくモデルになるものと高く評価しています。今回の西陣紋様同志会の調査研究では京都府立大学の応援を得ているのですが、京都市としてもこのような中小企業の産学連携と技術革新を支援していくことが求められています。
![]() 昨年12月国会において成立した「新事業創出促進法」に基づいて「中小企業技術革新制度」が設けられました。本制度は、アメリカの「中小企業技術革新制度(SBIR)」を模倣して創られたものです。アメリカのベンチャー企業の活況を支えている要因は種々指摘されていますが、その中でもSBIRは補助金や委託費など研究開発予算を有している省庁が、その予算の一定割合を中小企業に配分する努力義務を負うというもので、アメリカの中小企業政策の中でも最も成功しているもののひとつです。1970年代に入りアメリカの産業競争力が日本などに比べて遅れをとり始めたという事実に直面することとなり、戦略的に中小企業向けの連邦政府資金拠出を増やすことが望ましいと考えられるようになりました。
昨年12月国会において成立した「新事業創出促進法」に基づいて「中小企業技術革新制度」が設けられました。本制度は、アメリカの「中小企業技術革新制度(SBIR)」を模倣して創られたものです。アメリカのベンチャー企業の活況を支えている要因は種々指摘されていますが、その中でもSBIRは補助金や委託費など研究開発予算を有している省庁が、その予算の一定割合を中小企業に配分する努力義務を負うというもので、アメリカの中小企業政策の中でも最も成功しているもののひとつです。1970年代に入りアメリカの産業競争力が日本などに比べて遅れをとり始めたという事実に直面することとなり、戦略的に中小企業向けの連邦政府資金拠出を増やすことが望ましいと考えられるようになりました。
![]() 例えばSBIR創設前(1982年)の中小企業向け研究開発費はほぼ日米同レベルで日本円換算で約10億円でありました。ところが97年の度中小企業向け技術開発予算は日本が約62億円に対し、アメリカは20倍以上の約1,300億円となっています。そして日米両国の従業員500人未満の企業を対象とした調査によりますと、92年から96年の間に日本では雇用数が206万人増加したのに対して、アメリカでは同期間に1,183万人の増加をみているのです。さらにアメリカのSBIRの特徴は、まず省庁が研究開発課題を提示し、それに対して中小企業等が応募するという形式をとること。また研究開発費の無駄を無くし、かつより多くの中小企業に参加の機会を与えるため、実現可能性調査段階と研究開発段階と商業化段階の三段階方式を導入し、はじめの二段階で審査を行うと同時に資金供給も行うものです。特に第一段階の実現可能性調査段階すなわちフィージビリティ段階から支援しようというところに大きな特徴があります。
例えばSBIR創設前(1982年)の中小企業向け研究開発費はほぼ日米同レベルで日本円換算で約10億円でありました。ところが97年の度中小企業向け技術開発予算は日本が約62億円に対し、アメリカは20倍以上の約1,300億円となっています。そして日米両国の従業員500人未満の企業を対象とした調査によりますと、92年から96年の間に日本では雇用数が206万人増加したのに対して、アメリカでは同期間に1,183万人の増加をみているのです。さらにアメリカのSBIRの特徴は、まず省庁が研究開発課題を提示し、それに対して中小企業等が応募するという形式をとること。また研究開発費の無駄を無くし、かつより多くの中小企業に参加の機会を与えるため、実現可能性調査段階と研究開発段階と商業化段階の三段階方式を導入し、はじめの二段階で審査を行うと同時に資金供給も行うものです。特に第一段階の実現可能性調査段階すなわちフィージビリティ段階から支援しようというところに大きな特徴があります。
![]() 日本版SBIRもアメリカとほぼ同様のものですが、平成11年度の予算規模はわずか110億円程度であり、まだまだ不十分であり地方のニーズに合致しておりません。先ほどの西陣紋様同志会の企画でも日本版SBIRを利用することは困難であると思われます。その意味で、「京都市独自の中小企業技術革新制度」を創り、伝統産業や商業、観光などの分野で技術革新を図る中小企業等を応援していくことを提案するものです。政府と同じ課題設定型の仕組みをとりますが、そのテーマは京都の実状に合わせたものにすれば良いでしょう。また、関西TLOにおいて大学等の特許技術を中小企業に移転する場合に支援したり、あるいは工業試験場や染色試験場で民間企業と共同研究を行う場合に補助することも、この制度の中で実施してはいかがでしょうか。これらは必ずや京都の中小企業の技術革新を促進するものであると確信致します。以上京都市のこれまでの産業政策の総括を求めるとともに、私が申し上げました具体的提言についてご所見を賜りたいと存じます。
日本版SBIRもアメリカとほぼ同様のものですが、平成11年度の予算規模はわずか110億円程度であり、まだまだ不十分であり地方のニーズに合致しておりません。先ほどの西陣紋様同志会の企画でも日本版SBIRを利用することは困難であると思われます。その意味で、「京都市独自の中小企業技術革新制度」を創り、伝統産業や商業、観光などの分野で技術革新を図る中小企業等を応援していくことを提案するものです。政府と同じ課題設定型の仕組みをとりますが、そのテーマは京都の実状に合わせたものにすれば良いでしょう。また、関西TLOにおいて大学等の特許技術を中小企業に移転する場合に支援したり、あるいは工業試験場や染色試験場で民間企業と共同研究を行う場合に補助することも、この制度の中で実施してはいかがでしょうか。これらは必ずや京都の中小企業の技術革新を促進するものであると確信致します。以上京都市のこれまでの産業政策の総括を求めるとともに、私が申し上げました具体的提言についてご所見を賜りたいと存じます。
以上